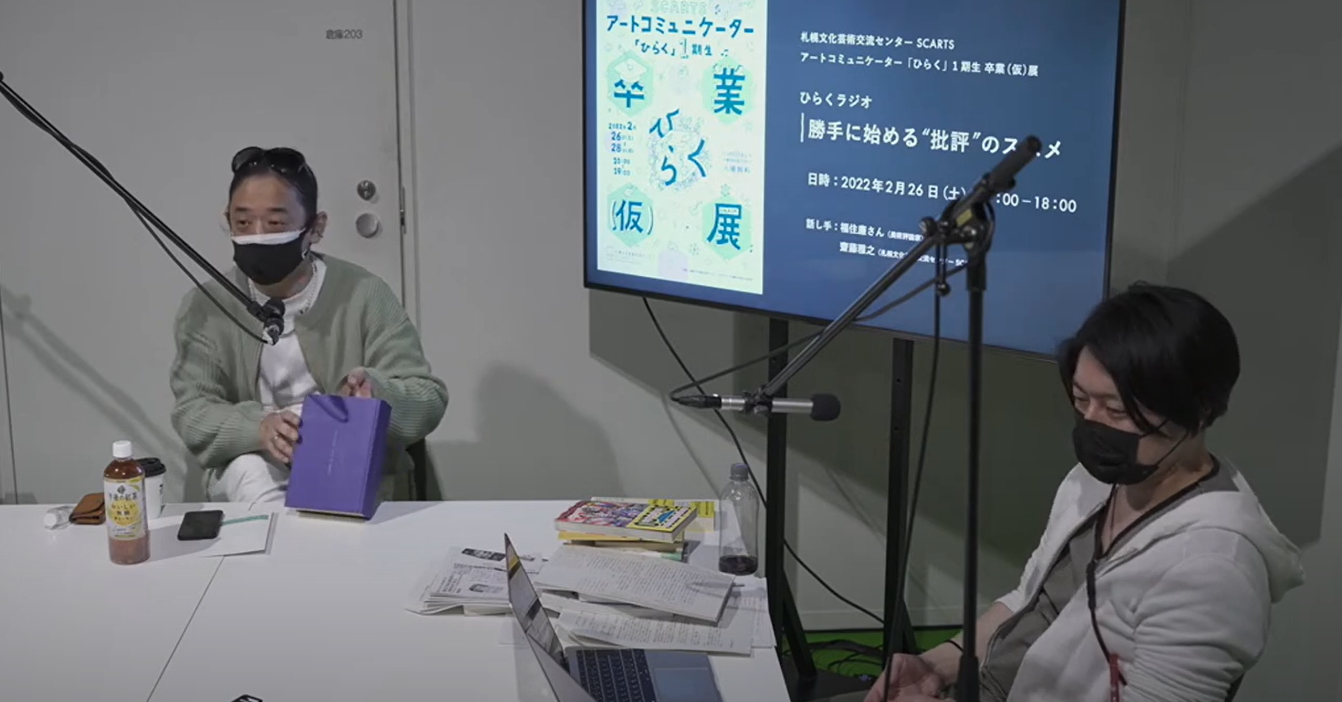ひらくラジオ①「勝手に始める”批評”のススメ」ゲスト:福住廉さん(美術評論家)
SCARTSアートコミュニケーター「ひらく」1期生 卒業(仮)展
2022 02/26
|ー2022 02/28
UP:2022/12/09
素人のプロフェッショナルな部分が見たい
齋藤|「アートコミュニケーター」と括ってしまうと忘れてしまいがちなのですが、参加されているみなさんそれぞれ、何かの道でプロフェッショナルだったり、すごい経験をしている人がたくさんいます。僕はアートコミュニケーション事業の担当者だなんて偉そうに名乗っていますが、自分ごときに何をできるんだろうといつも思っているんですが。
福住|さっきから「素人批評」というキーワードが出ていますが、それは便宜的な言葉で、今齋藤さんが言ったように素人として扱われている人も別の現場ではプロフェッショナルなわけで、それぞれに人生経験があるし、専門性も身につけている。だからそれを生かした表現や文章が見たいわけです。今の美術界や行政のアートプロジェクトなどは非常に浅い一面的なものしか評価しない傾向があると思います。本当はその下にもっと面白い豊かな土壌が広がっていて、それを見るためのパースペクティブ(※5)がアウトサイダーアート(※6)だったり、限界芸術(※7)だったりするわけですね。それを表現するためのツールのひとつが「書くこと」なんです。講座でも何度も言いましたけど、書くと自分の主観的な部分が出るんですよ。書き手の人となりとか主観的な部分とか好き嫌いとか、それを表現してほしいっていうのはさんざん強調してきたポイントです。素人という言葉の裏側にあるそれぞれのプロフェッショナルな部分を見たいし、それを共有したいんです。
齋藤|文章って自信を持ちにくいツールだと思うんですよ。誰でも文章には文句をつけられるから、それで自信を喪失して「私、文章が苦手で」みたいになっちゃう。もっと自信を持って書いてほしいし、文章は誰にでも開かれている、すごく力を持つツールなんだということは強く伝えたいですよね。
福住|僕もいろいろなところで教えていて、受講生の人が覚醒する瞬間というものを何回も見ていて、それは本当に面白いですね。明らかに乗って書いているのがわかるような文章があるんですよ。

齋藤|福住さんのこの赤字ってすごいんですけど、徹頭徹尾、文章の構造のことしか言わないじゃないですか。作品の解釈の仕方が正しいか間違ってるかなんて一切言わないで、いかにその人の思考を整理して他人と共有できるようにするかというところに絞って添削をしています。それはまさに、それぞれの書き手が持っているバックグラウンドや経験から生み出される唯一無二のものを最大限生かすためだと思います。しかし一方、福住さんご自身が書かれる批評では、評価するものとしないものをはっきりさせています。社会教育や大学で教える時と、ご自分がプロのもの書きとして書いている時とで、考え方を分けていたりはしますか?
福住|根っこは同じだと思いますけどね。特に学芸員の書く文章に多いけれども、結局どっちなんですかみたいな曖昧で歯切れが悪い文章はつまらないですよね。もっとはっきりと、いいものはいい、ダメなものはダメってやったほうが、自分が読者として読むときにも面白いと思うので、なるべく自分が書くときはそうしています。その手前に受講生の人が書くような文章があって、つまり私性とか主観的な部分をもうちょっと出しましょうよっていうのは、究極的にはそういう価値判断を明確にした批評文にまで持っていきたいからなんですよ。
齋藤|気をつけないと、空気を読み過ぎてしまうとか事なかれ主義になってしまうとか、集団の行動や力学の中でそういうものが生まれてきてしまうということだと思うので、そこで個人というものをどう捉えるかが大事というわけですね。
話は変わりますが、今話してきたような観点で、最近面白い本があったと聞いたのですが。
福住|社会学者の岸政彦さんが監修された『東京の生活史』(岸政彦 編、筑摩書房、2021年)という、1,216ページある分厚い本です。岸さんがインタビュアーを募り、150名に自分で取材対象者を決めてもらって、東京の街の中でどういった人生を繰り広げてきたのかを聞き出してもらう。そうして集まった膨大なライフヒストリーを一冊にまとめたものです。
アートコミュニケーターのみなさんも、これと同じようなことができるんじゃないかと思うんですよね。札幌という街並みを舞台にして、美術家やキュレーターだけではなく、アートに関わるいろいろな人たちがどういう風にアートに関心を注いで生きてきたのか、一つひとつの声を丁寧に拾い上げていく。それを一つに凝縮して発表することができれば、それは、美術館や大学の先生が書く札幌の美術史とは違う幅と厚みを持った、札幌のアートを巡る歴史になる気がします。
齋藤|インタビューする側がプロではないことについては、どういったところが面白いと思われますか?
福住|この本では、岸さんが取材対象者を決めたわけではなくて、インタビュアー自身に取材対象者を決めさせたので、ある程度個人的な信頼関係が構築された前提でインタビューが成り立っています。プロがいきなり話を聞く場合とは違って、個人的な関係性の中から出てくる話だから面白いんですよ。
齋藤|なるほど、「歴史」というと普通はプロの学者が専門的な方法で史実を読み解いて書くようなものですが、まさに「素人」だからこそアプローチの仕方があるわけですね。まさにアートコミュニケーターのみなさんが取り組んだら面白そうですね。そういったことで他に何か、福住さんがアートコミュニケーターに期待することはありますか?
福住|齋藤さんをみんなで批評するといいんじゃないかな(笑)。この間、オンラインで秋田公立美術大学の大学院の修了展で講評の仕事をしたときに学生が突然発言したんですよ。普段の大学の講評がむちゃくちゃつまんないという話を始めて、先生たちがピリついて「なんだ、大学批判か」みたいな(笑)。先生方も急に批判されたので驚いていたようですが、その学生に対して自分たちはこういう狙いで授業しているとかちゃんと説明して、つまりそこで対話が始まったわけです。学生は言葉が未熟だからそんなに論理的に説明できるわけでもないし、もう本当に言わずにはいられないという気持ちだけが先行してるような感じなんだけれども、でもそういう公式の場所で手を挙げて大学講評がつまらないと言った学生に、先生たちもちゃんと言葉で向き合ったわけでしょう。「批判」から「批評」に展開する原風景を見たような気がして、僕はそこに希望を感じましたね。
齋藤|今回のトークテーマは「勝手に始める”批評”のススメ」です。誰かに頼まれたり仕事で必要になったりということではなく、「ものを言いたい」「ものを書きたい」という初期衝動に任せてみんながひとりひとり勝手に批評を書き出したら面白いと思うし、福住さんの講座がそのきっかけになればいいなと思います。とはいえ反面では、今の時代、お手軽にものが言えてしまう、誰でも何でも言えるという妙な全能感みたいな雰囲気がありますよね。それはやっぱり良くないことだと思うんですよ、ヘイトとかポピュリズムとか。
福住|僕はもちろんヘイトはダメだと思いますが、そういう人こそ再教育できる可能性があるとも思っています。思想的に偏ったおじさんとかをたくさん集めて好きに書かせて、それらに僕は猛烈に赤を入れるわけです。むちゃくちゃ細かく厳密に(笑)。主張は否定しないけれども文章はダメだ、書き方が下手だということを徹底的に指導する中で再教育していくプロジェクトをやったら面白いんじゃないかな。
齋藤|言葉が貧しくなってしまっているということが今の不寛容な状況を生んでいるのは間違いないと思います。そこに対してどうリアクションができるのか。これは文化生産者が考えるべきことですよね。
福住|そうですね。
齋藤|どんな思いでこの文章講座をやってきたのか、なぜ講師として福住さんをお招きしたのか、今日の「ひらくラジオ」でアートコミュニケーターのみなさんに伝えられたと思います。福住さん、今日はどうもありがとうございました。
福住|ありがとうございました。
(※5) 様々なものの見方・考え方・視点。
(※6) 独学または趣味として素朴に制作された美術のこと。
(※7) 哲学者の鶴見俊輔が提唱した芸術概念。非専門的芸術家によって作られ、大衆によって享受される芸術のこと。
【プロフィール】
福住廉(ふくずみ・れん)/美術評論家
1975年東京都生まれ。和光大学人文学部卒業。九州大学大学院比較社会文化学府博士後期課程単位取得退学。2003年、美術出版社主催第12回芸術評論で佳作受賞。「共同通信」で毎月展評を連載中。美術雑誌、ウェブマガジン、新聞、展覧会図録、作品集などにも寄稿している。『今日の限界芸術』ほか著書多数。現在は秋田公立美術大学大学院准教授、東京藝術大学大学院美術研究科テクニカル・インスタラクター。社会教育の現場でも講師を務めている。
聞き手:齋藤雅之(SCARTSアートコミュニケーション事業担当(当時)、(公財)札幌市芸術文化財団所属)